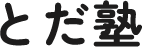こんにちは。とだ塾です。
今回は英語が苦手な生徒へのアプローチについてお話しします。
英語を見ると拒否反応が出る。
英語の細かい違いにイライラする。
そんな英語が特に苦手な方や、
「そういう子にどう接したらいいかわからない」と悩んでいる方の参考になれば幸いです。
以前担当した生徒さんのお話です。
その生徒さんは入塾時、英語に対して強い苦手意識がありました。
英単語を読むのも、英文を目で追うのも、すぐに疲れてしまう。
苦手なものに向き合うことは、想像以上にしんどいものです。
その子の話を聞いて、なるほどなと思ったことがいくつかありました。
“I”の後ろには”am”を置くと習ったのに、”I am make”はダメだと言われる。
“Are you make〜?”と聞いたら、「違う」と言われる。
ほぼ合っているのにバツにされたり、自分で何回も間違えることにイライラする。
英語という教科の特徴ですが、惜しいのにバツになることが多く、
その繰り返しが「英語ってイヤやな」という苦手意識につながっていきます。
とだ塾では、まず「惜しい!」とちゃんと認めます。
“Are you make?”でも、〇をつけることがあります。
厳密に言えば10点くらいしかないような答えでも、
大きく丸をつけて、80点くらい取れた気分になれるようにしています。
その子の現状のレベルに合わせて採点をし、
「ここだけは覚えてほしい」という点に絞って直してもらいます。
こういうやり方は、学校のテストにはすぐには結びつきにくいです。
学校のテストでは「間違いのない解答」が求められるため、当然ながら厳しい評価になります。
でも、もともとテストが不向きな子も存在します。
そういう子でも、スピーキングのような「なんとなく伝わればOK」という場面では、
パッションでうまく乗り切ってしまうこともたくさんあります。
そして、驚くかもしれませんが、
先ほどの子には進学校でゴリゴリやるような品詞分解を教えてみたところ、英語が急に得意になりました。
品詞分解とは、文章を文型(SVOC)で区切ったり、
かたまりで名詞になるか、形容詞になるか、副詞になるかを見分けることです。
たとえば、
〜ingの形は大きく分類すると
-
①進行形
-
②動名詞
-
③形容詞的用法(後置修飾など)
-
④分詞構文
に分かれますが、どの使い方かは文章の位置によって判断されます。
「この文章はSVOとおまけのM(修飾語)でできてる第3文型やな。」
「目的語位置に〜ingがおるから、これは動名詞やね。」
こういった教え方は中学校ではあまりされませんし、
「英語が苦手な子にそんなこと無理じゃない?」
と思われるかもしれません。
ですが、多くの中学校では品詞や文型を無視して
「なんとなく違いわかるよね?」で理解させられることも多く、
先ほどの子は、まさに「違いをしっかり理解できないから分からない」という状況だったようです。
語彙力を無視すれば、品詞や句節の理解だけなら中学生でも小学生でも可能です。
また、こういった子は、高校レベルの「ちょっと進んだこと」に触れることで、
「みんなと違うことしてる!」という感覚が刺激になり、やる気につながることもあります。
この子の場合は極端な例だったかもしれませんが、
こちらも先入観を捨てて指導すること。
生徒にとって「ちょっと頑張れば手が届くくらいの難易度」で取り組んでもらうことが大事だと、あらためて実感させられました。
苦手なものに向き合うことは、簡単なことではありません。
できた瞬間を一緒に喜び、わかりたい気持ちを少しずつ育てる。
とだ塾は、目の前のテストだけでなく、
その子の小さな一歩を一番大切にする塾でありたいと思っています。